“努力できる人”と“続かない人”の脳の違いと、凡人が「続ける脳」を育てる戦略的ステップ
どうも、いわしブログです。
突然ですが、あなたの本棚に「積読(つんどく)」はありませんか?
「今年こそは英語を!」と買ったまま、ホコリをかぶった参考書は?
「健康のために!」と意気込んでポチったランニングウェアは、今やパジャマになっていませんか?笑
え、私ですか? もちろん、あります。
私たちは毎年、毎年、誓います。「今度こそ、やるぞ」と。
そして、その誓いはたいていの場合、春の雪のように儚く溶けていきます。
一方で、世の中には「努力を継続できる人」が確かに存在します。
毎日淡々とブログを更新する人。
雨の日も風の日もランニングを欠かさない人。
難関資格を一発でパスする人。
彼らを見るたび、私たちはこう思います。
「あの人は、意志が強いんだな」
「私とは、根性が違う」
「きっと、特別な才能があるんだ…」
しかし、
もし、その違いが「意志の強さ」や「根性」といったフワッとした精神論ではなく、「脳の配線」の違いだとしたら?
そして、
その「配線」は、生まれつきではなく、後天的なトレーニングで「作り変える」ことができるとしたら?
今日は、そんな「努力」と「継続」の謎を、脳科学の観点から丸裸にしていきます。
「なぜ、あの人は努力できて、私は続かないのか。」
その「悩み」を科学的に解剖し、「続ける脳」を育てるための超・戦略的なステップをご提案します。
この記事を読み終える頃には、「自分は意志が弱い」という呪いから解放され、「なるほど、脳をそう“しつけ”ればいいのか」という“攻略本”を手に入れているはずです。
努力できる脳 vs 続かない脳:戦いは「報酬」で決まる
「努力できる人」と「続かない人」。
両者を分かつ最大のポイントは、「ドーパミン」の扱いです。
ドーパミンは、俗に「快楽物質」と呼ばれますが、「モチベーション物質」と呼ぶことにしましょうか。
「それをやれば、快感が得られるぞ!」と、行動を起こすための“ガソリン”の役割を果たします。
続かない人の脳:「今すぐ、楽に」が最優先
まず、私たち「三日坊主」側の脳の仕組みを見てみましょう。
私たちの脳は、基本的に超・省エネ設計です。生き延びることを最優先にプログラムされています。
新しいこと(勉強、運動)を始めようとすると、脳は「おっと、面倒なことを始めたぞ。エネルギーの無駄遣いだ。やめろ」と全力でアラートを鳴らします。これが「めんどくさい」という感情の正体です。
さらに、「続かない人」の脳は、「目先の報酬」にしかドーパミンが出にくい傾向があります。
- (勉強)→(1時間後、疲れるだけ)→ やらない
- (運動)→(30分後、汗だくで苦しい)→ やらない
- (スマホ)→(1秒後、楽しい動画が見れる)→ やる!
- (お菓子)→(1分後、甘くて美味しい)→ 食べる!
「英語ペラペラ」や「引き締まった体」という未来の大きな報酬よりも、「今すぐ得られる小さな快楽」に、脳がハイジャックされてしまうのです。
これは意志が弱いのではなく、脳の生存本能として、ある意味「正常」な反応とも言えます。
努力できる人の脳:「未来の喜び」を“前借り”している
では、「努力できる人」の脳はどうなっているのでしょうか。
彼らは、苦痛に耐える「ドM」なのでしょうか?
違います。
彼らは、「努力のプロセスそのもの」や「未来の報酬を想像すること」で、ドーパミンを出す術を心得ているのです。
スタンフォード大学の著名な神経科学者、アンドリュー・ヒューバーマン教授は、「努力できる人は、努力の最中に感じる“苦痛”や“摩擦”そのものに、快感を紐づけている」と指摘します。
どういうことか?
「続かない人」は、ランニングの「苦しさ」だけを感じます。
「努力できる人」は、その「苦しさ」の先に待っている「達成感」や「成長している感覚」をリアルに想像し、“報酬を前借り”しているのです。
彼らにとって、キツい筋トレは「苦行」ではなく、「理想の体に近づくための“快感スイッチ”」になっています。
難しい勉強は、「面倒」ではなく、「新しい知識を得る“知的興奮”」になっています。
つまり、彼らはドーパミンが出る「タイミング」が違うのです。
この「報酬回路」の配線の違いこそが、両者を分かつ決定的な差なのです。
司令塔「前頭前野」と職人「線条体」の連携
ドーパミンだけでは、話は半分です。
「努力できる脳」を機能させるには、あと2つの重要なプレイヤーが必要です。
1.長期的な司令塔「前頭前野(ぜんとうぜんや)」
前頭前野は、脳の「CEO」です。
理性、計画、長期的な視点を司る、最も人間らしい部分です。
「続かない人」は、このCEOが「目先の快楽(スマホやお菓子)」を求める“原始的な脳”(大脳辺縁系)に負けてしまいがちです。
「今はこれをやるべきだ!」というCEOの指令が、現場(=自分の行動)に届きません。
「努力できる人」は、この前頭前野が強い。
彼らは「今はキツいが、半年後の試験に合格するためには、この1時間を勉強に充てるべきだ」と、未来から逆算して「今」をコントロールする力を持っています。
2.習慣化の職人「線条体(せんじょうたい)」
前頭前野が「やるぞ!」と決意しても、毎回それを実行するのは大変です。CEOがいちいち現場のネジを締めていては、疲弊してしまいます。
そこで登場するのが「線条体」。これは「習慣」を司る部位です。
私たちが歯磨きをする時、「よし、右上の奥歯からだ!」「次に裏側!」と、いちいち前頭前野で考えていないですよね? ほぼ無意識でやっています。
これが「習慣化」です。
「努力できる人」は、努力を「決意」の領域(前頭前野)から、「習慣」の領域(線条体)へ移すのが非常にうまいのです。
彼らは、もはや「頑張って」走っていません。
「朝起きたら、顔を洗う」のと同じレベルで、「朝起きたら、ウェアに着替える」が自動化されています。
一度、線条体に「これは自動でやることです」と登録されてしまえば、脳はエネルギーを消費しません。
ここまで来ると、努力はもはや「努力」ではなく、ただの「日常」になります。
【実践編】凡人が「努力できる脳」を育てる3つの科学的戦略
「わかった、わかった。脳の仕組みはもういい」
「要するに、ドーパミンを出して、前頭前野を鍛えて、線条体で習慣化すればいいんだろ? どうやって!」
お待たせしました。ここからが本題です。
意志の力(根性論)に頼らず、脳の仕組み(科学)を利用して「続ける脳」を育てるための、具体的な戦略をご紹介します。
戦略1:ドーパミンをハックせよ。「プロセス報酬」の設計
「続かない人」は、報酬(ゴール)が遠すぎます。
「フルマラソン完走」や「TOEIC900点」では、脳がドーパミンを出す前にガス欠になります。
戦略:報酬を「結果」ではなく「行動」に置く。
ジェームズ・クリアー氏の世界的ベストセラー『アトミック・ハビッツ(邦題:ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣)』でも強調されているテクニックです。
- (誤)「痩せたら、あの高い服を買う」
- (正)「ジムに行ったら、好きなプロテインを飲む」
- (誤)「単語帳を1冊終えたら、ゲームをする」
- (正)「単語を10個覚えたら、カレンダーにデカい花丸をつける」
ポイントは、「自分がコントロールできる行動」をしたら、即座に小さな報酬(自己肯定感でもOK)を与えることです。
「カレンダーに花丸をつける」という行為は、バカバカしいようですが、脳にとっては強力な報酬(視覚的な達成感)になります。
これを繰り返すと、脳は「勉強(行動)=デカい花丸(快感)」と学習します。
こうして、本来は苦痛だったはずの「プロセス」そのものに、ドーパミンが出るようになっていくのです。
戦略2:前頭前野をだませ。「1分ルール」と「If-Thenプランニング」
私たちの脳(特に原始的な部分)は、「変化」を極端に嫌います。
「さあ、1時間勉強するぞ!」と意気込むと、前頭前野が「うわ、デカいタスクが来たぞ…」と怯み、先延ばしが始まります。
戦略:「やる」ことのハードルを、脳が気づかないレベルまで下げる。
「やりたい習慣」を、1分以内に終わる行動に分解します。
- 「毎日ランニングする」→「ランニングウェアに着替える」(1分)
- 「毎日ブログを書く」→「PCを開いて、タイトルを1行書く」(1分)
- 「毎日読書する」→「本を1ページだけ開く」(1分)
バカらしいですか? でも、これが最強の初動戦略です。
「ウェアに着替える」ことだけを目標にすれば、脳の抵抗はゼロに近くなります。そして、いったん着替えてしまえば、「まあ、ちょっとだけ走るか」となるのが人間です。
これをさらに強化するのが、心理学者ピーター・ゴルヴィツァーが提唱する「If-Thenプランニング(もし~したら、こうする)」です。
- (曖昧な目標)「今夜、勉強する」
- (If-Then)「もし、夜7時になったら、すぐに本を1ページ読む」
「いつ、何をやるか」を具体的に決めておくだけで、実行率は跳ね上がると言われています。
これは、前頭前野が「いつやろうかな…」「何からやろうかな…」と悩むエネルギーをゼロにし、行動へのスイッチを「自動化」するテクニックです。
戦略3:線条体を攻略せよ。「アイデンティティ」の書き換え
最後の戦略であり、最も強力な戦略です。
習慣化のゴールは、「努力」を「無意識」に落とし込むこと(線条体で自動化すること)です。
しかし、「私は意志が弱い人間だ」と思っている人が、いくらテクニックを使っても、どこかで破綻します。なぜなら、脳は「自分が信じている自分(アイデンティティ)」と矛盾する行動を嫌うからです。
戦略:「行動」を変えようとするのではなく、「自分」の定義を変える。
- (行動目標)「私は、毎日ランニングを頑張る」
- (アイデンティティ)「私は、ランナーである」
「ランナー」は、雨が降ったからといって走るのをやめません(なぜなら自分はランナーだから)。
「ランナー」は、「今日は走りたくないな」とはあまり考えません(なぜなら走るのが日常だから)。
「私は健康的な人間だ」
「私は学び続ける人間だ」
最初はハッタリで構いません。
小さな行動(戦略1, 2)を1回クリアするたびに、「ほら、やっぱり私はランナーだ」「私は学び続ける人間だ」と、自分自身に「証拠」を提示していくのです。
「ウェアに着替える」(行動)→「私って、ランナーやん」(アイデンティティの強化)
「1ページ本を読む」(行動)→「私って、知的な人間じゃん」(アイデンティティの強化)
この「証拠集め」を繰り返すうちに、脳の線条体は「ご主人様は“ランナー”なんですね。了解です。明日から自動で足を動かすようにセットしておきます」と、あなたの自己イメージを行動に一致させようと働き始めます。
ルフィだって「海賊王に俺はなる!」と宣言し、アイデンティティの強化をしているのです。
こうなれば、もう「努力」は必要ありません。
それが「あなた」だからです。
まとめ:あなたは「意志が弱い」のではなく、「脳のトリセツ」を知らなかっただけ
「努力できる人」と「続かない人」の違い。
それは、「意志」や「根性」といった精神論ではありませんでした。
- ドーパミン(報酬)の出し方
- (続かない人)目先の快楽に負ける。
- (努力できる人)プロセスや未来の想像で、ドーパミンを出せる。
- 前頭前野(CEO)の強さ
- (続かない人)CEOが原始的な脳に負ける。
- (努力できる人)CEOが「今」をコントロールし、長期的な目標を優先できる。
- 線条体(習慣化)の活用
- (続かない人)毎回、意志の力(前頭前野)で頑張ろうとして疲弊する。
- (努力できる人)行動を「自動化」し、エネルギー消費ゼロで実行する。
そして、私たち凡人が「続ける脳」を育てるための戦略は、根性論ではなく、脳を科学的に「しつける」ことでした。
- 戦略1(ドーパミン): 報酬を細かく分けて、「行動したらすぐにご褒美」で脳をハック。
- 戦略2(前頭前野): 「1分ルール」で抵抗をなくし、「If-Then」で悩む隙を与えない。
- 戦略3(線条体): 「私は○○な人間だ」と決めて、小さな行動アイデンティティ書き換えをする。
もう「意志が弱いから…」と自分を責める必要はありません。
さあ、まずは何から始めましょうか?
「ランニングウェアに着替えてみる」?
「本を1ページだけ開いてみる」?
私は参考書を1ページだけ開いてみることをやっていこうと思います笑
その小さな一歩が、脳の配線を変える、偉大な一歩になるはず。
いわしブログでした。

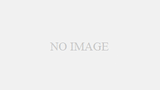
コメント